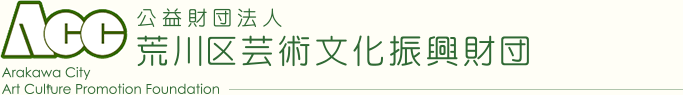No.122 松本 聰(まつもと さとし)
微生物とうまく付き合いを
土は宝庫…鉢植え多く、住みよい町
 「農学」と聞いて、どんなイメージを描くでしょう。食糧や牧畜の増産、農地、林地の拡大に貢献する--という従来の印象は、高度経済成長を経た現在、大きく変わっています。ひとつは遺伝子(DNA)の組み替えなど、ミクロの世界を扱う分野(分子生物学)が広がったことですが、一方で、私たちの生活と「環境」とを結び付ける、マクロな視点の研究も活発です。松本さんは、この環境科学分野で、めざましい研究を重ねています。
「農学」と聞いて、どんなイメージを描くでしょう。食糧や牧畜の増産、農地、林地の拡大に貢献する--という従来の印象は、高度経済成長を経た現在、大きく変わっています。ひとつは遺伝子(DNA)の組み替えなど、ミクロの世界を扱う分野(分子生物学)が広がったことですが、一方で、私たちの生活と「環境」とを結び付ける、マクロな視点の研究も活発です。松本さんは、この環境科学分野で、めざましい研究を重ねています。
四国の四万十川は、日本を代表する「残された清流」でしたが、1980年代、流域の人口が増え、生活排水の流入が進むに従って、ここでも水質悪化が問題になり始めました。松本さんは、高知県の橋本大二郎知事の依頼を受け、独自の水処理装置を考案。危ぶまれた日本一の清流を数年間で蘇生させた実績で、高い評価を受けています。
この装置のユニークさは、周辺の環境に元来あった素材だけを使い、合成化学素材に頼らないことでした。木炭、堆積した落ち葉(堆肥)、石灰石などを順番に詰めた、高さ2メートル、長さ12メートルのろ過装置。これを流入する支流や排水溝にいくつかずつ設置して、川の水がこの装置の中を通って出て行くようにしました。
「水質が悪化すると一口に言いますが、その実態は、多彩な生き物が棲みにくくなり、限られた種類だけが突出して繁殖する、という状態のことなんです。こうした生態系では、特定の種類の微生物以外の種類がいなくなるため、窒素、リンなどが消費されずに大量に水中に残る。そうして富栄養化、水質悪化が進むのです」
逆に言えば、多様な生物が棲めるように川を変えてやれば、昔の清流が蘇ることになる訳です。木炭や石灰は過剰のリンを、落ち葉の堆肥中で増えた微生物が窒素を吸着するなど、93年から始まったこのプロジェクトは、想定通りの効果を表してきました。これに国連環境計画(UNEP)も注目、途上国の水質改善策の切り札に導入することが決まったほか、千葉県の手賀沼、茨城県の霞ヶ浦などの水質改善にも、この装置が活躍し始めました。
松本さんは、「微生物といかにうまく付き合うか」が、生活のキーワードだと言います。
「だから微生物の宝庫である土は、大切なもの。私が住む荒川区の下町には、広い庭が無い代わりに、路地や歩道を利用してさまざまな鉢植えが並んでいます。スプーン一杯の土には、約百億の微生物が生きており、これを利用しない手はありません」
魚屋さんでもらえる発泡スチロールの「トロ箱」一杯の土には、4人家族の家庭の生ゴミを肥料として吸収してしまうほどの処理能力があると言います。
「堆肥を作るため市販されている菌類もありますが、何も入れなくて良いのです。生ゴミからビニールや金属を除いて、トロ箱の鉢植えの端から順番に土の中に入れて、かき混ぜてやる。冬は発酵が進みませんが、春から秋にかけてなら、これだけで、十分生ゴミを堆肥に変える力があるのです。もちろん、臭いもしませんよ」
夫人の実家がある、東尾久2丁目に住んで10年余。以前住んでいた文京区の高台に比べて、物価は2割安く、商店街が多いので買い物にも便利。また休日などは静かなので、住み心地がとても良いそうです。
「本郷の研究室にも30分ほどで通勤でき、たいへん便利です。途中で見かけるツツジ、ボタン、アサガオや路地裏の植木も楽しく、常磐線の踏み切りでは、通り過ぎる貨物列車が落とす雪煙に季節のうつろいを知らされる。心を開けば、いたるところに自然ありです」
文・小出重幸
カメラ・岡田 元章