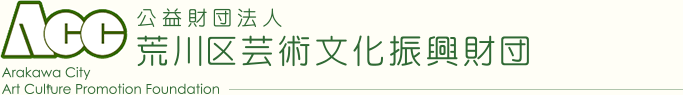No.208 武関 翠篁(ぶせき すいこう)
竹工芸作家
文化交流使
| 伝統は尊いもの、それを現代に生かしていきたい |
伝統工芸がとりもったドイツでのうれしい巡りあわせ
昨年の秋、武関翠篁さんは文化庁の文化交流使としてドイツを訪れた。ハンブルク工芸美術館が収蔵する早川尚古斎(しょうこさい)の竹工芸作品を調査・確認することが主な目的だった。武関さんは、人間国宝である五代目早川尚古斎に指導を受けた縁もあってのドイツ訪問となった。初代・尚古斎は、幕末から明治にかけて活躍した人で、かつて日常消耗品とされていた、しかも中国の模倣が主流だった竹籠作りを、日本独自の手法を確立し工芸にまで高めた人。その貴重な作品66点が、ハンブルク工芸美術館に保存されていたのだ。「130年も前のものが、しかも無傷なんです。雨が多いハンブルクの気候のせいもあるけれど、大事に保存してくれていたことに対して感謝の気持ちでいっぱいでした。そして、感謝する一方で、早川尚古斎の技術の確かさを、まざまざと感じました。日本の技術の素晴らしさを確信しました。だからこそ時を経ても残っている。尚古斎は作品に、自分の名前だけでなく制作時の年齢も彫って入れているんです。侍のプライドですよね。五代目の教えを受けた自分としては、感慨もひとしおでした。さらには、ワークショップの際、ドイツの方が〝自慢の籠〟だと言って持ってきたのがなんと私の作品。驚きました」
武関さんは、うれしい思いを胸に、視察のため、その後ドイツの数ヵ所を回り、
ドイツの人々との交流を深めた。そして、なんと、シュトゥットガルトでのぞいた美術品オークションには、父・武関翠月さんの作品が出品されていたというのだ。「うれしい巡りあわせに感激しました」
どんなに細くなっても失われない張りつめたぴんとした力強さに惹かれる
 武関翠篁さんは武関家の三代目。祖父・翠心さんが戦後、栃木からここ荒川区西日暮里に移ってきて工房を開いた。
武関翠篁さんは武関家の三代目。祖父・翠心さんが戦後、栃木からここ荒川区西日暮里に移ってきて工房を開いた。翠篁さんは、第一日暮里小学校、道灌山中学、竹台高校と進んだ純正荒川ッ子。
物心ついた頃から家業の手伝いをし、ごく自然に父たちの後を継ぐようになったという。彼は、竹の魅力をこんなふうに語る。
「竹というのはね、どんなに細くなっても力のあるものでしてね、その張りつめたぴんとしたものが持つ力強さ、そこに惹かれます。そうした素材の魅力と軽やかさ、〝透かし〟の魅力。竹は一本一本が強いですから、空間をあけても大丈夫なんです。その透けて見えるところが実にいい」
翠篁さんの作品には花籠が多く、そこには美しい透かしの手法が活かされている。また、使用するのは新しい竹ばかりではない。例えば、囲炉裏で使われていた200年前の〝煤竹(すすだけ)〟なども素材として用いられる。黒ずんだ深みのある素材感がなんとも魅力的だ。
そんな繊細な竹工芸だが、聞いてみると道具はいたってシンプル。しかも数も少ない。
「木工の人は鉋(かんな)を何種類も使うけれど、竹は全然違いますね。私の場合、小刀1本、鉈3本、手あんばいだけで削っていくのが中心の仕事なんです」
それで美しい作品を仕上げるのだから、その技術たるやなまはんかな事ではない。
「そうそう、ドイツで早川尚古斎のレプリカを作っていまして、これが一見そっくり。でも、触ると全然違う。本物はずっと滑らかなんです。日本の場合は、1ミリ以下の竹でも必ず面取りをするんですよ。面取りをしないと壊れるというわけではないんです。美意識ですかね。日本人の繊細さをあらためて感じました。そういう美意識を、私も大切にしていきたいですね。
それにしても、伝統というのは非常に尊いものだと思います。技術にしろ、道具にしろ、不要なものが全然ない。必要なものだけが残っている。先人が長い年月をかけて到達した素晴らしいものだと思います。私は、そうした200年前のものを、現代のデザインに生かしたいと思っています。
具体的にいうとデザインの中の〝動き〟ですかね。スタティックでなくダイナミックな竹工芸を目指したいと思っています」