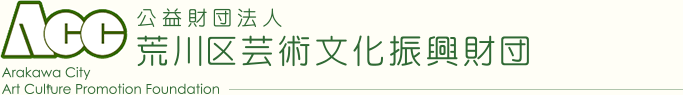No.146 押田 洋子(おしだ ようこ)
憧れのパリで磨いた感性
私の自慢“荒川の下町っ子”
 窓から望むのはエッフェルの尖塔。手前の坂道にひっそりと佇むのは、ゴッホがすんでいたアパルトマン。
窓から望むのはエッフェルの尖塔。手前の坂道にひっそりと佇むのは、ゴッホがすんでいたアパルトマン。
フランスのパリ18区。モンマルトルの丘の中腹に立つ、そのアパルトマンの5階にある部屋は、小さくともかけがえのない「城」でした。年を重ねた国の歴史的な建造物。豊かな食文化。
「消費社会」だけではない、住み続ける、使い続けることの大切さ。美しく、知的であることの重要さ。大人がステキに生きている世界でした」
そんなパリに憧れ、パリに行くために、せっかく就職した広告代理店を退社。
「若かったからできたこと。でも、後悔なんてひとかけらもなかったですね」
それだけ、花の都は押田さんを圧倒しました。
コピーライター、イラストレーター、エッセイスト。三つの顔を持つ押田さんは1939年、南千住に生まれました。第六瑞光小学校時代、今でも、ある若い女性教諭のことが忘れられない、といいます。
「物がない時代でした。クラスの半分は戦争で親を失った子どもたちで、雰囲気も暗かった。そんな私たちの前に、いつも素敵なワンピースを着た女性の新任教諭が赴任したんです」
その若い女性教師は、民主主義やクラシック音楽の素晴らしさを子どもたちに教え、押田さんは故郷の外には、新しい世界があることに胸を躍らせます。
女性には学問は不要、との偏見がまだ残る時代に、名門、津田塾大学英文学部へ入学。アメリカの文豪、ヘミングウェイの世界を学びました。
62年に卒業後、博報堂に入社し、コピーライターに。休暇で訪れたパリの虜になり、74年に退社と同時に、念願のフランスへ遊学。その後、フリーのコピーライターとして、現在も広告業界で活躍しています。
81年からは、「漢文も嫌いだったし、できれば行きたくなかった」という中国の食文化にも目覚めました。
北京、四川、上海、広東の四大料理はもとより、海南島、台湾、香港などの食文化の追求に、訪中歴は40回を超えます。
イラストレイターとしての才能が開花したのは、50才を過ぎてから、ちょっとした偶然がきっかけ。
「広告のしごとで、その中国へ出張中、暇つぶしに何となく建物や料理のイラストを描いたんです。それをたまたま年賀状に使ったら、もらった相手が偶然どこかへ紹介して--」
太さ2ミリのサインペンで描かれる繊細なタッチと、淡い色調。どこにでもある日常的な風景や食べ物が、押田さんの手にかかると、別の生命が吹きこまれたかのように、生き生きと輝きます。
その数々の作品は、NHKの料理番組「きょうの料理」のテキストの扉絵にも採用され、昨年暮れには、新宿のギャラリーで初めての個展も開催されました。
「私は荒川の下町っ子というのが自慢なんです。真っ正直で正義感が強くて、義理人情に篤くて」
パリで毎日のように食べた焼き立てのパンも、中国で初めて口にした「銀絲巻(インスジュアン)」もおいしかったけれど、「終戦の頃彫刻職人だった父が私のために焼いてくれたデコボコのパン。トウモロコシの粉で焼いたからボロボロと崩れちゃうのですが、あのパンも、最高においしかった」。
読売新聞記者・臼井 理浩