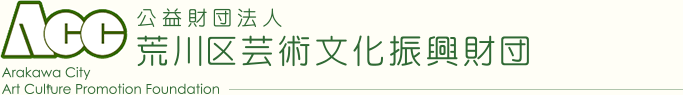No.135 濱野 恭一(はまの きょういち)
「患者第一」に二つの目の顔
「世界一」に燃える"日暮里っ子"
 世はミレニアムブーム。濱野さんも区切りの年の真っただ中で、超多忙の日々を送っています。
世はミレニアムブーム。濱野さんも区切りの年の真っただ中で、超多忙の日々を送っています。
「東京女子医大は今年創立100周年を迎え、その記念事業として総合外来棟を11月に竣工させます。完成すれば、1日当たり5000人から6000人の患者が見込まれ、日本一いや世界一の規模となるでしょう」場所は隣接する税務大学校の跡地(新宿区若松町)。
「大蔵省から払い下げてもらいましたが、私学は資金集めから運営まで自分たちでやらなくてはなりません。いかにコストを抑えるか、頭を悩ませています。人手を要する医療はリストラが難しい一方で、赤字になることは許されませからね」
まさに経営者の言葉です。濱野さんが東京女子医大の理事に就任したのは平成11年。半世紀近く握ってきたメスをソロバンに変えました。
「ところが実は一週に一度は診察、時には手術を行っているんですよ。患者第一主義の精神をいつまでも持っていたいですからね」
千葉大学医学部を卒業するとすぐに同大の第二外科に入局。そこで出会った恩師が中山恒明先生でした。消化器外科の世界的権威。中山先生の教えは厳しく、一日も休みのない日が続きました。たまりかねた濱野さんが「日曜くらい休ませてください」と直訴すると、返ってきた言葉が、「患者に休みがあったら休め」。
往年を懐かしむように眼鏡の奥が細くなりました。中山先生の教訓は今も濱野さんの胸に生き続けているのです。
「先生はよく言っていました。我々は病気を治すんじゃない。病気の人を治すんだ、と」
この二人の師弟がそろって東京女子医大に迎えられたのは昭和41年のことです。消化器病センターのオープンとともに、濱野さんは外科助手に。同大の誇るセンターシステムのスタートと同時に、最前線での活躍が始まったのです。
以来、助教授、教授と消化器外科の道をまい進し、救急救命センター長なども歴任しました。所属学会は14にも及び、海外の学会のメンバーにもなっています。いきおい教育研究にも熱が入ります。
「女子だけの医学の専門大学など世界でも類がないでしょう。うちは従来の医学教育を解体し、生理学や解剖学といった科目もないのです。入学してすぐに5、6人のグループに分かれ、テーマごとに先生の指導のもと、自分たちで学習を進めてゆきます。チュートリアルシステムという、全く新しい教育を行っています。」
その目は再び大学運営者となり、メラメラと燃えました。
実家は旧「日暮里3丁目」。父が小児科医を開業していました。現在住んでいるところは、そこから徒歩5分ほどの東日暮里五丁目です。
「昭和20年4月13日の空襲で焼け出されましてね。鶯谷駅の向こう側に逃げて振り返ると、一つの町が全部燃えていました。あの壮絶な光景は今でも忘れられませんね」
濱野医院の庭先にも焼夷弾が落ちました。その角張った金属筒を精米器に利用してしまったというから、あっぱれです。まさに下町っ子のたくましさを物語るエピソード。
「西尾久には東京女子医大の第二病院もありましてね。本当に荒川の人にはよくしてもらっています」
長女は同じ大学の外料医。次女は歯料医。長男は建築の仕事に携わっています。
「男は爽やかなるがよきなり」が好きなフレーズ。でも女子大ではなじまないのでは、と水を向けると、その時はこう言い換えるとか
「女は優しきがよきなり」
読売新聞記者・中村 良平
カメラ・岡田 元章