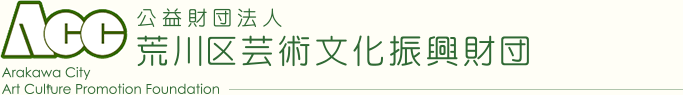No.118 尾身 周三(おみ しゅうぞう)
昔の民家を描き歩いて30年
好きな町、夢は荒川線風景の作品展
 真っ赤な夕焼け空を背景にかやぶき屋根の民家が二、三軒。手前には清流が流れる──日本の原風景ともいうべき郷愁に満ちた里のたたずまいを写実的なタッチで描き続けて約三十年。「民家の尾身」として知られ、その絵は絶大な人気です。これまでの作品の数は「さあ、何万点になりますかねえ」。
真っ赤な夕焼け空を背景にかやぶき屋根の民家が二、三軒。手前には清流が流れる──日本の原風景ともいうべき郷愁に満ちた里のたたずまいを写実的なタッチで描き続けて約三十年。「民家の尾身」として知られ、その絵は絶大な人気です。これまでの作品の数は「さあ、何万点になりますかねえ」。
民家を描くようになったのは二十代後半、ある美術展で「ウクライナのタベ」という、夕日に映える農家の白壁を描いたソ連画家の作品に感激したのがきっかけでした。日本が高度成長を果たしたころで、物質的に豊かになった半面、何か大切なものがなくなっていくと感じていた人も多く、尾身さんの作品は、そうした日本人の心情に強く訴えるものがあったのでしょう。
ただ、「民家の画家」にとって困るのは、対象とする民家そのものが年々消えていくこと。尾身さんはアユの友釣りが趣味で、福島あたりの山あいへ出かけては、同時にかやぶき民家を″物色″するのですが、「夏にいい家を見つけて、秋にスケッチしに行ったら、もう壊されていた」などということもしばしば。時代の流れで「それもしかたのないこと」といいます。
作品集に載せられた略歴には「新潟出身(東京生まれ)」とありますが、これは「古い民家を描く画家が東京出身ではまずいかな、と思って…。新潟は父の故郷なんです」。尾身さん、実は荒川生まれの荒川育ち。奥さんは山形生まれで、結婚したのは「この人と一緒になれば、いつでも山形へ行ける」というのが動機だった(?)そうで、″田舎への憧れ″はずっとあったようです。
もともと絵を描くのが好きで、小学五、六年を通った第九峡田小で、画家志望の黒部という先生が担任になり、尾身さんの画才を認めてくれて「他に何にもできないんなら、絵でも描け」と勧めてくれました。この幸運な出会いもあって、絵を職業にすることは自然な選択でした。
生まれたのは、南千住の回向院の近く。小学校は第三瑞光、第三峡田、第九峡田と三回変わり、中学は荒川五中に通いました。
「こどものころは、まだ周りに空き地や畑がたくさんありました。西新井橋あたりの荒川へ泳ぎにも行ったものです」。途中、畑でトマトを失敬したら、持ち主のおばあさんに見つかり、「取るんなら、熟した下のはうの実を、自分で食べる分一つだけ持っていけ」と言われたこともありました。尾身さんの作品には、よく、畑を打ったり、家の前でなにか燃やしている農婦が登場しますが、その時のおばあさんの姿が重なっているのだそうです。
現在五十五歳。小さいころは何回か区内を転居しましたが、現在の荒川五丁目にはもう四十年以上住んでいます。「まだ下町の素朴さが生きているし、昔の下町の人情が残っています。いい所ですよ。町内会の役員をしている幼なじみもいます。散り散りになった仲間も、祭りになればみんな戻って来ますしね。離れられませんよ」
次は、都電荒川線沿線の風景を措いてみたいそうです。「これまでは、民家を描くのに忙しくて余裕がありませんでしたが、自分なりの荒川線を措いて、区内でその作品展を開きたい、というのは、昔からの夢だったんです」。円熟の絵筆に期待しましょう。
読売新聞記者・大越 英雄
カメラ・岡田 元章