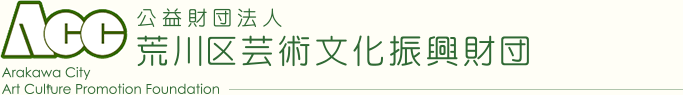No.115 増田 みず子(ますだ みずこ)
故郷千住、昔の川も懐かし
落ち着ける下町、秋には長編発表
隅田川の川沿いで暮らした時代を、増田さんは、そんな風に言います。
ものごころついたころ、多感な少女時代、そして青春の日々、増田さんの風景には、いつも隅田川が流れていました。現在はアクロシティと名を変え高層マンションが立ち並ぶ場所にあった「千住製紙」、そこに勤める父親の都合で、増田さんの家族は川沿いの社宅を転々とします。
小学生、中学生時代は川向こうの足立区や松戸市、中学三年だった昭和三十八年から十年間はど、荒川八丁目と南千住六丁目で暮らしたそうです。
「水は汚い、臭いもひどかった。その悪臭が学校まで漂って、友達がバタバタ倒れるなんてこともありました」
日本全体がまだ貧しく、増田さんの家とて例外ではなく、汚れた黒い川を見るにつけ、「きらびやかな東京の生活なんて無縁」と感じる日々でした。
「美しいものに憧れるというのは若い時分によくあることでしょう。だから、きれいな山とか川のせせらぎなんかに憧れがありました。清流を眺めていると、頭の中がカラッポになるというか、心が洗われるという感じですし・・・」と増田さん。
「でも、世の中がどんどん良くなる時代でした。未来が希望に輝いていましたしね」
希望という言葉にすら希望を持てなくなった現代の若者に比べれば、確かに「幸福」だったかもしれません。
東京農工大の農学部を卒業後、日本医大に助手として勤め始めた増田さんは、昭和五十二年ごろから小説を書き始めます。その三年後には、勤めを辞めて専念、作品が次々に芥川賞候補となり、昭和六十一年、三十七歳の時『シングル・セル』で泉鏡花賞を受賞します。
「結婚したのも、ちょうどその頃。そんな時、隅田川を見てたら、黒い水面に映るように、いろんなものがわきだしてきた。ふと、自分の原点は黒い水面の、この隅田川なのかな、なんて」
結局のところ、自分はやはり千住の人間なんだ、と強く感じたといいます。
「千住が故郷なんですね。風景がすべて体に焼きついている。土地というのは、不思議なもので、全然違うところに住むと、かえって疲れてしまう。下町が一番落ち着くみたいです。ここに住む人たちは、曲がったことはしない、ウソはつかない、正直というか、かけひきがない。何を考えているかが分かるんです」
だから現在も墨田区に居を構えています、と笑う増田さんです。
しかし、隅田川は変わりました。
「水がきれいになり、堤防なども整備されて、川が狭くなったみたい。以前は堤防なんか無くて、川が遊び場でした。千住大橋の手すりの上や常磐線の鉄橋の上を歩いたりとか、川沿いの造船所や石炭置き場に潜り込んだり、つないである無人のボートに乗ったりして。危ないなんて注意する大人もいなかったし、子供にとっては最高の町だったかもしれません」
そんな思い出を話す時の顔には、作家ではなく、下町の元気な少女の面影がのぞきました。
ここ一年ほど作品を発表していなかった増田さんですが、漱ごろには雑誌「新潮」に「か色」という長編小説が掲載され、樋口一葉の評伝も出版される予定です。ゴルフのフリーライターのご主人と仲よく二人暮らし。より一層の活躍が期待されます。
読売新聞記者・吉弘 幸介
カメラ・岡田 元章