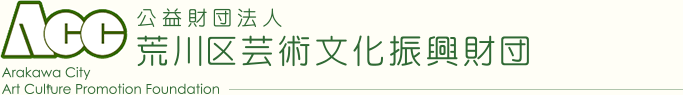No.113 田中 一郎(たなか いちろう)
大使館勤務、酒断って小説も
「踏切りの音で天気のわかる」荒川っ子
 手を伸ばせば、通り過ぎる電車に届きそうなほど。そんな都電・荒川線の沿線に住んで二十年近くになるという田中さんには、不思議な特技があります。
手を伸ばせば、通り過ぎる電車に届きそうなほど。そんな都電・荒川線の沿線に住んで二十年近くになるという田中さんには、不思議な特技があります。
「踏切のカンカンカンという音で、その日の天気が分かるんですよ」
雨の日、晴れの日で微妙に違うその響きから、判断するというわけです。
そんな口ぶりから、肩書のいかめしさとは全く違う、気さくで温和な人柄が伝わってきます。生まれも育ちも荒川区という生粋の下町っ子だからでしょう。
「実家は尾久小学校のすぐ前。だから、学校でイタズラなんかすると、先生が家に駆け込んでくる。嫌でしたね。学校がもっと遠ければいいのにと思いましたよ」
その小学校入学直前に東京大空襲で被災。荒川区一帯はもちろん、東京中が焼け野原になりました。
「避難先で、あの物資がない時代にどこにあったのか、炊き出しにサケ缶が出てきたのには驚きました」
困った時には助け合おう、そんな下町の人情が、しみじみうれしかったと語る田中さんです。
ワンパクだった小学校時代の級友とは、今でも毎年泊まりがけで旅行にいくほどの親密ぶり。尾久界隈での飲み会には四十人も集まるということです。
「荒川区の人間だからでしょうね。港区なんかじゃ、こうはいかないと思いますよ。地元で仕事をしている人が多いからでしょうか」
荒川六中から足立高校、慶応大学と進み、外資系の貿易会社に就職しましたが、三年ほどで退社。しかし、そこでの経験が、今でも役に立っているそうです。
その後、しばらくジャーナリストの大森実さんがつくった国際問題研究所の仕事をして、昭和四十六年、スウェーデン大使館に入りました。
そのハードな大使館勤務のかたわら、イギリスの作家、モームの研究を続け、二年前に、その成果を「秘密諜報員サマセット・モーム」(河出書房新社)という本にまとめました。
「月と六ペンス」「人間の絆」などの作品で知られるあのモームが、実は英国の秘密諜報員で、CIA(アメリカ中央情報局)の設置に関して大統領にアドバイスした大物スパイだったというのだから、驚きです。
モームゆかりの地の取材、埋もれた資料の発掘など、勤務を縫っての労作です。
「三年半、この本を書くために酒は全く飲みませんでした。睡眠時間は減ったけど、体のためには差し引きゼロかな」
この六月には、ゴッホの自殺の謎に迫る作品を刊行予定で、さらに、画家ゴーギャンに関する著作も準備中です。
「ものを書くというのは、格闘技だと思う。仕事が、きつければきついはど、いい発想が生まれる」
闘いの状況が困難で、追い込まれるはど、意外な力が生まれるということかもしれません。
「荒川の血が流れている」という田中さん。それだけにまちを思い、そこに住む人たちを思い続けています。
「僕はね、荒川区から突出した人物が生まれてくるような時代になったという気がするんです」
伝統のある地域だけに、今こそユニークな人材が出る、という言葉に力がこもります。
お礼を言って帰ろうとした玄関先で、「今度はぜひ一杯やりましょう」と温かな言葉が返ってきました。
読売新聞記者・吉弘 幸介
カメラ・岡田 元章