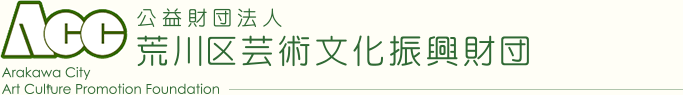No.112 山田 邦子(やまだくにこ)
デビュー18年 小説続々、車の免許も
幼児の思い出ふくらむ下町っ子
 東尾久八丁目で生まれ、区内で過ごしたのは三歳まで。でも、生まれ故郷の思い出は届きることのない泉のように湧き出て来ます。
東尾久八丁目で生まれ、区内で過ごしたのは三歳まで。でも、生まれ故郷の思い出は届きることのない泉のように湧き出て来ます。
「今は荒川信用金庫がある場所に、父の会社の社宅がありました。一軒家で庭がすごく広くて、花壇もあった。私は小さなころからチョロチョロ動き回っていたので、お使いとか、いろいろな初体験はすべて荒川でしたね」
なかでも鮮明に覚えているのは、自宅前を走る都電を横断する時のこと。
「母から十円のおこづかいをもらっては、向かいの駄菓子屋に行きました。今見ると狭い道路なのに、一世一代の覚悟で渡りましたね。やっとの思いで店に着いたら、ポケットに穴が開いていて、お金が無かったことも」
おもちゃのリカちゃん人形の収集家としても有名です。
「リカちゃんの発売前、タミーちゃんという人形があって、その妹のペパーちゃんを熊野前のおもちゃ屋さんで買ってもらったのが最初です。おままごとセットをお父さんの前に持っていき、これだけしかないと、ねだった覚えがあります」
懐かしい思い出の数々は、これまで八冊書いた小説の題材にもなっています。自伝的な「一家ランラン」には、荒川から江東区に引っ越したころのことを綴りました。
「下町はゴチャゴチャしていて、小説のネタがいっぱい。今は新宿に住んでいますが、先日、近所で事件があって、警察の方に『お隣はどなたですか』と聞かれたんです。『たしか、おばあさんが住んでいるはず』と答えたら、実は違っていた。それに比べ、下町はどこのだれかがはっきりしていて、好きですね」
小説執筆の取材のため、久しぶりに区内を訪れることもあるとか。
「何だか怖そうな路地があって、昔はいつも猛ダッシュで通り過ぎていましたが、大人になって初めて見たら、質屋さんがありました。道理で大人の人が肩を丸め、ススッと足早に歩いていたんですね」
中学からは目白の川村学園に通い始めますが、やはり、荒川との緑は途切れることはありませんでした。
「仲良くなった友達が町屋に住んでいて、よく泊めてもらいました。お嬢さま学校というのは、しゃべらないと、だめなんですよ。下町だったら『この花、きれいね』と言っただけで相手に伝わるのに、花がどうきれいで、何と思ったかまで話さないと分かってもらえないんです」
山の手に住む友人が増えても、下町への愛着は変わりません。
「山の手だと、おやつと言えばクッキーや紅茶が出てきますが、下町ではミカンに、おせんべい。でも、コタツにおせんべいで良かったと、つくづく思いますね」
早いもので、デビューして十八年。最近まで月曜から金曜までのレギュラー番組に出演し、休む暇もありませんでしたが、やっと余裕も生まれました。念願だった車の免許を取り、今は新作小説「ヘアメイク神井結の芸能界ミステリー案内パート2(仮題)」の執筆に余念がありません。でも、エッセーを含め、著書は十冊以上に上り、そろそろ荒川の話も居きたのでは?
「頭の中の貯金は底をついてきました。でも、思い出って、育っていくものなんですよ。スライド式に、いつまでも心に残っています」
少女の心を忘れず、いつも明るい「邦ちゃん」の原点は、この荒川だったのです。
読売新聞記者・多葉田 聡
力メラ・岡田 元章