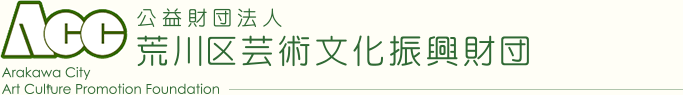No.108 工藤 一嘉(くどう かずよし)
年半分は被災地、観測点へ
近くて花のよい町に「もう四半世紀」
 おとなりは文京区の東大キャンパス。根津神社裏手の丘の上に、同大学の「地震研究所」はあります。この二階の研究室をお訪ねしました。本棚に整然と並べられた膨大な資料。コンピュータの画面はスクリーンセイバーの画像を流しつづけ、静かに主の着席を待っています。学者の城、というイメージにぴったり。
おとなりは文京区の東大キャンパス。根津神社裏手の丘の上に、同大学の「地震研究所」はあります。この二階の研究室をお訪ねしました。本棚に整然と並べられた膨大な資料。コンピュータの画面はスクリーンセイバーの画像を流しつづけ、静かに主の着席を待っています。学者の城、というイメージにぴったり。
「でも一年の半分近くは、被災地や観測点に出かけていて、ここでのんびりと暮らしてはいられないんです」
地震学はフィールドワークの学問だと言います。阪神大震災(一九九五年一月)が起きた時は、すべての予定をキャンセル、二日後には倒壊の砂塵も治まらない神戸市三宮の街の中にいたそうです。
「私が現場を踏んだ被災地の中では、死者約8千人を出したメキシコ地震(一九八五年)のメキシコシティの高層ビル群の被害が、最もひどかったのです。でも阪神大震災は、死者こそ少なかったものの、建物被害はこれを上回る惨状でした」
専門は、地震のゆれを測定する「強震計」の観測網を使って、地震現象を解明し防災に役立てること。「一般に期待されているほど、科学は地震の本質を明らかにできていないのです。どんなところが、揺れがひどいか、被害が大きくなるのはどんな条件の時かなど、おおよその事は把握できますが、自然現象の多様さは地震学の知識を超えています。地道にデータを積み重ねることが、何よりも大切です」と説明してくれました。
区民にとって地元、荒川区の安全度が気になるところですが、「通常の地震では、堆積層の厚い土地の揺れが大きくなりやすいのです。都内では、大学がある本郷の台地などは堆積層が薄く、荒川地域の堆積層の上にある私たちの地域は、残念ながら地震の揺れは大きくなりやすい。日ごろからの心構えが大切です」と、注意を呼びかけています。
「でも、大地震が今すぐに来るという逼迫性はありません。百年くらいの間には考慮しなければなりませんが……」
静岡県に生まれ、父親の転勤と共に、山形県や北海道で育ち、仙台で学生生活をしと、各地の生活を体験しているそうです。それでも夫人の実家のある西日暮里の住民になって四半世紀近く。「人生の半分を区民として過ごしたことになりますね」
東大の先生の中でも、工藤さんのように歩いて研究室に通える恵まれた人は、ごくわずかです。西日暮里駅近くの自宅を出ると、駅の西側の坂道を登って浄光寺、養福寺の並ぶ尾根道を歩き、谷中の寺町を下って根津神社前に、その裏手へ抜けて研究所まで、二十五分くらいとのこと。
「花の季節には諏方神社の桜を見たり、谷中墓地の桜並木を通り抜けて、ゆっくり歩きます。朝はまだ酔客もいないし、とても静かなお花見ができますよ」
二人の娘さんは、第六日暮里小学校、道灌山中学校時代、そろって東京荒川少年少女合唱隊で活躍していました。
「『こころで歌い上げる』ことを大切にした先生方の指導方法、その成果を目の当たりに見せてくれる演奏会のステージに、強い印象を受けました。隊員の両親たちとのふれあいを通して、世話好きで、人のつながりを何よりも大事にする下町の気質に触れた気がします。振り返れば研究室やフィールドにいることが多く、地元意識の希薄な私を地域社会に結び付けてくれたのは、合唱隊の存在だったのかもしれませんね」
「山手線、地下鉄を使えば、都内のどこでもすぐに行ける便利さが、一番。こういう所に住むと、なかなか他の土地には引っ越せません」という工藤さん。若いころ手がけたチェロを弾く時間を捻出したい、という夢を抱き続けています。
読売新聞記者・小出 重幸
カメラ・岡田 元章