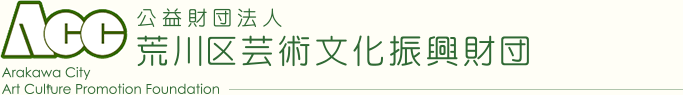No.99 村松 増美(むらまつますみ)
あふれる活力とユーモア
飛行機から英語へ、恩師のおかげ
 東京・赤坂のサイマル・インターナショナルの会長室に現れた村松さんは、やや小柄なごく普通の紳士に見えました。ところが、ひとたび語り始めると、その良く響く声、歯切れのよい語り口、しなやかな身のこなし、どれをとっても実に若々しい。とても六十六歳とは思えないエネルギーにあふれていました。
東京・赤坂のサイマル・インターナショナルの会長室に現れた村松さんは、やや小柄なごく普通の紳士に見えました。ところが、ひとたび語り始めると、その良く響く声、歯切れのよい語り口、しなやかな身のこなし、どれをとっても実に若々しい。とても六十六歳とは思えないエネルギーにあふれていました。
村松さんは、書籍出版、英語教育、通訳など多岐にわたる事業を手掛けるサイマル・グループの総帥、というより英語同時通訳の草分けで今も第一人者、さらに何冊もの著書を持つ文筆家、と言った方が通りがいいでしょう。先進国サミットでの機転のきいた名通訳でも有名です。
勉強も仕事も遊びも他人の三倍というエネルギッシュな生き方は、荒川ですごした若い日々に身につけました。
戦争中の昭和十八年、荒川区・汐入にあった東京と立航空工業学校(現・都立航空高専) に入学しました。
「親父が模型飛行機の店を開いていたこともあって、空に憧れていました。本当は飛行機乗りになりたかったが、乗り物にすぐ酔ってしまう質でしてね、それじゃあ造る方に進もうと思ったのです」
当時は、住んでいた浅草から市電で南千住まで来て、そこから歩いて学校へ。
「まだ、隅田川の水もきれいで泳げました」が、やがて勤労動員。学校の隣にあった大日本紡績の工場で零式戦闘機の鋲打ち作業をする日々でした。
昭和二十年三月十日の東京大空襲で焼け出され、両親と四人の弟たちは山梨県に疎開。村松さんだけは残って、同じ境遇の学友とともに学校に寝泊まりし、終戦までをしのぎました。二十三年の卒業まで、敗戦の混乱のなかで学生生活が続くわけです。
そんな青春真っただ中の村松さんが、英語にひかれはじめたきっかけは、恩師の今石益之先生でした。
「先生は、チャールズ・ラムの『シェイクスピア物語』やラフカデイオ・ハーンの『怪談』などを教材に、実にいい授業をされた。いま考えると、非常に学のある人だったんですねえ」
飢えと背中合わせの闇市焼け跡の時代、若者は知的なものにも渇いていました。
「ラムは子ども用に易しくシェイクスピアを紹介しているし、ハーンの作品は、英語で日本のことを読める面白さが新鮮でした。通訳になって、その知識を、とっさに使って助かったこともあります」
ある時、学校の近くにいた捕虜と片言の英語で話をしたそうです。
「ジャワで捕虜になったオランダ兵だと分かって、とにかくコミュニケーションできたことがうれしかった。昔から、ものおじせず、好奇心も強かったんです」
もっとも、翌日、先生にキツくお仕置きされたそうですが。
敗戦で航空機産業は壊滅。村松さんは、英語の勉強を本格的に始めました。それから後のアメリカ体験、通訳としての活躍ぶりは、『私も英語が話せなかった(正・続)』『だから英語は面白い』『指導者たちのユーモア』(いずれもサイマル出版会刊)などの著書に詳しいので、ごらんください。
毎冬二十日ほどはスキーを楽しみ、この日も「あすから軽井沢、白馬に出掛けます」とのことでした。「英語で落語をしたい」「日本人の笑いを外国に紹介したい」─と老後の夢が山はどあるそうですが、「老後」はまだまだ先のようです。
読売新聞記者・長山 八紘
カメラ・岡田 元章