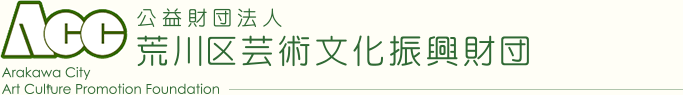No.94 石田 幸雄(いしだゆきお)
演劇少年、万作門下で開花
芸にもよかった"下町育ち"
 東京・千駄ヶ谷にある国立能楽堂は、この日の狂言公演で、笑いにつつまれていました。「腰祈」の舞台で、シテとして祖父役を演じたのが石田さん。腰が曲がっているこの老人を気の毒に思った孫の山伏が、祈って腰を伸ばしてやることにするのですが、行力が強過ぎて、祖父の体は反り返ったり縮んだり、てんやわんやの騒ぎ。このあたりを絶妙に演じ、会場からはやんやの喝采を浴びました。
東京・千駄ヶ谷にある国立能楽堂は、この日の狂言公演で、笑いにつつまれていました。「腰祈」の舞台で、シテとして祖父役を演じたのが石田さん。腰が曲がっているこの老人を気の毒に思った孫の山伏が、祈って腰を伸ばしてやることにするのですが、行力が強過ぎて、祖父の体は反り返ったり縮んだり、てんやわんやの騒ぎ。このあたりを絶妙に演じ、会場からはやんやの喝采を浴びました。
公演を終え、汗をふきつつ現れた石田さんは、まだ四十七歳。がっしりした体に柔和な笑顔。「着物を着ているときは、このほうがサマになるので」と正座をしながら、荒川区で育った幼少年時代のことを語ってくれました。
生まれたのは南千住。祖父は指物師、父もおけ屋や装飾などの職人です。「私の家系は代々、親父の後を継がない職人で、私の場合は、伝統芸人の職人になりました」。
町屋や千住など、父親の仕事の関係で、数えきれないぐらい引っ越しをしたそうですが、思い出にある荒川区は、「まだ空き地もいっぱいあり、鳥もちをつけて虫をとって遊びました。第七峡田小一、二年のころは、荷馬車が通っていました」
戦後の荒廃から日本が立ち直るころのこと。「テレビもあれば、紙芝居もあり、駄菓子屋にもいりびたる。豊かさと貧しさの両方がありましたね」。
貸本屋も人気で、「『ゴルゴ13』のさいとう・たかをさんの作品や、つげ義春さん、『鉄人28号』が人気になる前の横山光輝さんの本を借りだし、低学年のころは、まんがばかり読んでいました」。
そんな少年が、のめりこんだのは、このころ全盛だった映画。荒川区には当時、七、八軒の映画館があって、年間二、三百本は見たそうです。
演劇は尾竹橋中学の先生の影響ではじめ、都立忍岡高校二年のときに「狂言は演劇の役にたつ」と聞き、狂言師として名高い野村万作さんのもとに入門。卒業後、プロとしてこの道に進みました。
狂言は、とにかく師匠のまねをすることから始まる世界で、「余計なクセをきれいになくさなければ大成しない。自我を一度殺してしまい、体が狂言そのものにならないといけない」厳しい世界だそうです。
この道に入ってからは映画観賞もやめ、十年間は稽古に舞台に没頭。「年間二、三百の舞台をこなしながら、現場で学ぶ日々でしたから、大変と感じる余裕もない生活でした」と修業時代を振り返る石田さん。
「親父もおふくろも下町生まれのせいか、私も『しこうき』(飛行機)『しろしま』(広島)と、『し』と『ひ』の区別が出来ず、苦労しましたね」。また「跳び箱を跳ぶにも、いつ手を離したら跳べるのかと考えてから跳ぶタイプだったので、まずは体を動かしてから考える狂言の世界に慣れるのに、苦労もありました」。
それでも「庶民の生活が息づいていた荒川区で育ったことは、大衆芸能である狂言をやるうえでよかった」そうです。
三歳で舞台にたった長男淡朗ちゃんは八歳。能・狂言の子方として活躍、石田さんも狂言「遊兎の合」を主宰し、伝統芸能の継承とともに新作狂言に取り組むなど、忙しい毎日を送っています。
十月十五日には、国立能楽堂で、「平家物語」の新たな魅力を発掘する新作語り物「千尋の底」を上演します。
荒川の人にも、ぜひ舞台を見てもらいたいものです。
読売新聞記者・鵜飼 哲夫
カメラ・岡田 元章