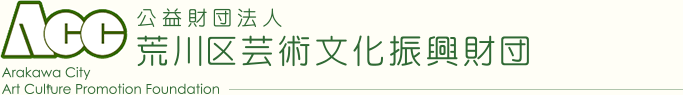No.63 小室 等(こむろ ひとし)
<荒川>こそ心の原点
今は全国を歌い歩く喜び
 日本でフォーク・ソングが市民権を得てかれこれ三十年になります。これがニュー・ミュージックと呼ばれるようになって二十年と少し。今では演歌や歌謡ポップスを押しのけて、日本の音楽の中心的な流れになりましたが、そのフォーク界の草分けの何人かの名前を挙げると、必ず登揚するのがこの人です。
日本でフォーク・ソングが市民権を得てかれこれ三十年になります。これがニュー・ミュージックと呼ばれるようになって二十年と少し。今では演歌や歌謡ポップスを押しのけて、日本の音楽の中心的な流れになりましたが、そのフォーク界の草分けの何人かの名前を挙げると、必ず登揚するのがこの人です。
葛飾区掘切で生まれて間もなく一家は堀切から尾久へ。「二十歳までここで過ごしました。宮前小学校から中学と高校は私立の聖学院。そして多摩美大の彫刻科を卒業しましたが、僕のフォーク歌手としての根底には荒川という意識が流れています」
一九七三年に「東京」というアルバムを出しました。今から二十一年前と亭えば、荒井由実の「ひこうき雲」、井上陽水の「氷の世界」などが若者たちの心をとらえ始め、「シクラメンのかほり」「心もよう」などのヒットしたころでもあります。
「ここでいう東京とは荒川区のことです。僕にとっての東京は、すなわち荒川区ですからね。ちょうど脱都会がはやっていたころで、例えば、傍らの仲間の岡林信康も東京を離れて山の中で生活を始めたのですが、脱出してみても、アンチ都会の意識を持ってみても、何の解決にもならない訳でしてね。都会に残って出来ることは何かと考え、歌を作りました」
その年を含めて二回、都内を回る「二十三区コンサート」を行い、「二十三区コンサート・東京旅行」というアルバムも出していますが、「確か、荒川区では区民会館小ホールでした。ゲストは詩人の白石ありす、井上陽水でした」。
東京人には故郷、あるいは故郷意識、田舎がないとも言われますが、荒川が故郷という意識で?
「故郷と言えるかどうかは別にして、東京ではあっても独特の場所であることは確かですね。原っぱと家内工業の工場がある町で、生粋の東京とはちょっと違って、チャキチャキじゃないけれども、すごいバイタリティーがある町です」
育った家は小規模な工場の敷地の一角でしたが、父親が電気工事店を経営するかたわら、旅回りの一座などを迎える芝居小屋を持ち、そんな環境の中で、高校生のころからギターを手に歌い始めます。最初は、だれでもがそうであったように、アメリカンフォークのコピー。「キングストン・トリオやピーター・ポール&マリーのコピーでしたが、やがて自分の思いを曲にと考え、作り始めました。ですが、どうやっても複製の域を出ないのですね。その時、自分らしさとは何だろうかと真剣に考えました。そこで出てきた意識が、荒川です。これが生涯のテーマになりました」
最初に結成したグループはPPMフォロワーズ、続いて六文銭。「出発(たびだち)の歌」、「だれかが風の中で」の大ヒットを持っています。また、フォーク歌手だけで作ったことで話題を呼んだフォーライフ・レコードの初代社長も務めました。
そして五十歳になった今は─。
「はい、コンサート活動を続けています」と、トレードマークのひげに囲まれた顔が目を細め、優しいほほえみを浮かべながら、こう話してくれました。
「年に八十回くらいでしょうか。ギターを手に一人で作った歌を歌い歩く。田舎が多く、もちろん僕の名前も曲も知らない、生の音楽を初めて聴いたというおじいさんが感激してくれたりします。祖父が、旅回りの表具師で浪曲師でしたが、今の僕は、とても似た生活をしています」
読売新聞記者・寺村 敏
カメラ・水谷 昭士