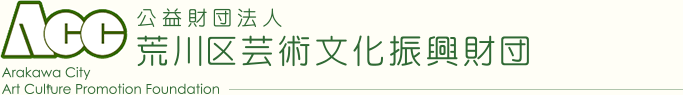No.19 深津 鉱三(ふかづ こうぞう)
<要>が肝心、舞台扇は入念に
玉三郎や時蔵から特別注文も
 かつては、東京に百人以上いた扇子づくりの職人も、今は二十人ぐらいしかいないそうです。
かつては、東京に百人以上いた扇子づくりの職人も、今は二十人ぐらいしかいないそうです。
そのなかでも深津さんは、中村時蔵や坂東玉三郎など、今を時めく歌舞伎役者や日本舞踊の家元から特別注文を受けるほどの腕前で、昭和五十九年には、荒川区の無形文化財保持者に認定されています。
まず、東京きっての名人といえるでしょうが、万事控え目で、おだやかな人柄です。
扇子づくりをはじめたのは、祖父の井上利兵衛さんでした。江戸時代の末期に、日本橋榑正(くれまさ)町(高島屋デパートの裏)で長屋を持ち、質屋も経営していた利兵衛さんは、明治維新の時「ご一新だから何か商売でも始めよう」と思い立ち、町内の扇子屋さんに勧められて、扇子店を開きました。
この利兵衛さんは、日本橋区の区画整理を担当し、その功績でアメリカ旅行の恩典を与えられましたが、「危ないからおよしなさいよ」と奥さんにいわれ、断念したそうです。
その後、浅草に移り父親の弥一郎さん、長兄の貫介さんが相次いで亡くなったので次兄の福次郎さんと深津さんが家業を継ぐことになったわけです。
深津さんは母方の養子になった関係で、姓が違います。
扇子の本場は京都。
「地紙や竹の骨など材料の仕入れ先は京都だし、扇子のことを知るために京都に住みました」
若いころ地紙屋の離れを借りて「ぶらぶら遊んでいた」といいますが、おそらく修業の日々だったのでしょう。
扇子づくりの職人がたくさん住んでいる五条通りに所帯をもち、大阪心斎橋に小売店を開き…と順調に進んだかのようでしたが、次兄は浅草で、深津さんは大阪で戦災にあい、戦後は、東京に戻って荒川区に居を移し、もう四十年近くになります。
扇子づくりには、たくさんの工程があって、とても説明しきれませんが、肝心なのは、やはり要(かなめ)だそうで「これがしっかりしていないと、開いたり、しめたりがうまくいかない。とくに舞台で使う扇子には、神経を集中します」といいます。
能の家元が、扇子の柄を軽く握っただけで扇子のよしあしがわかるそうで「これはダメです。しまってませんね」と、きびしくいったそうです。
時蔵や玉三郎が使う扇子は、中啓といって、親骨の上の方が、外に反っているバチ形の扇です。
扇子の骨もお祝いの時は朱、不幸の時は黒ときまっているし、芝居の内容によって絵柄も違ってくるので、深津さんは歌舞伎や芝居をよく観に行くし、玉三郎とも会って話しながら勉強するそうです。また宮内庁関係の仕事も手がけています。
息子さん二人は、すでに独立して勤め人。後継者は次女の佳子さんの気持ち次第で、目下見習中だそうです。
荒川区については、「めったに外へ出ませんが、街並みもきれいになったし、区役所の人も、ずいぶんサービスがよくなりましたね。戦時中にくらべれば、まるで天国と地獄です」と明るく笑いました。
文・篠原大